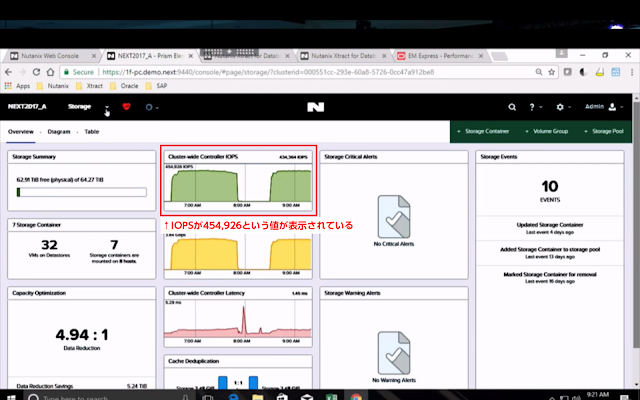今回は、AFSにおけるよく聞かれる質問についてご紹介をしたいと思います。
Q.AFSは、どのエディションで利用が利用できるのですか?
AFSを利用する際にはライセンスが必要という話は第1回目に出てきました。具体的に言うと、Nutanix上でAFSを利用する際には、AFSを立てるクラスターに「Ultimate」のライセンスが適用されている必要があります。
Nutanixクラスター内でのライセンス混在は通常あり得ませんので、Nutanix5ノードで稼働している場合、そのクラスター全体がUltimateライセンスで構成されていれば、そのままAFSを利用可能です。
現在利用しているNutanixクラスターのライセンスが、ProもしくはStarterの場合、AFS単独ライセンスを手配すれば、利用可能となります。
このAFS専用ライセンスは、Nutanixのノード数でカウントされます。上記のようにNutanix5ノードで稼働しているNutaixクラスターでProライセンスを利用している場合、5ライセンス分のAFSライセンスを購入すれば、AFSが利用可能となります。
Q.AFSは、Nutanix以外の基盤で動作するのですか?
AFSは、Nutanix上で動作するために設計された仮想アプライアンスのため、Nutanix以外の基盤ではハイパーバイザーの種別を問わず動作させることはできません。
Q.Nutanix XpressでもAFSは利用できますか?
残念ながら、XpressモデルではAFSは利用できません。これは、AFSが、ABS(Acropolis Block Service)の機能を利用することに起因しており、Xpressモデルは、ABSをサポートしていないことから、利用不可となります。そのためAFS単独ライセンスを購入しても利用できないので注意が必要です。
Q.ウイルス対策ソフトはインストールできるのですか?
AFSのアプライアンス自体にウイルス対策ソフトをインストールすることはできません。ただし、AFS2.2からICAPベースのウイルス対策ソフトオフロード機能により、アンチウイルスに対応しています。
ただし、AFS2.2のリリースノートに「Note: For the AFS 2.2.0, AFS AV only supports Kaspersky Security 10 for Windows Server.」という記載があり、対応しているウイルス対策ソフトは、カスペルスキーのウイルス対策ソフトに限定されています。
ただし、このICAP機能は、「Kaspersky Security 10 for Windows Server Version 10」のマニュアルを読む限り、「日本向けライセンスの制限により、Kaspersky Security の ICAP および RPC ネットワークストレージ保護機能は使用できません。ソリューション「Kaspersky Security for Storages」のサポートおよび販売は日本の地域では行っていません。」
という記載があります。
(参考)Kaspersky Security 10 for Windows Server 管理者用ガイド 製品バージョン:10 P43より
つまり、事実上日本では、現状利用できないことになります。
今後、他のウイルス対策ソフトウェアにも対応するかと思いますので、現状はクライアントのウイルス対策ソフトウェアでの対策というのがソリューションとなります。
(参考) Kaspersky Security 10 for Windows Server 管理者用ガイド 製品バージョン:10 P43
https://docs.s.kaspersky-labs.com/japanese/ks4ws_admin_guide_ja.pdf
(参考) AFS2.2リリースノート (要Nutanix Portalログイン)
https://portal.nutanix.com/#/page/docs/details?targetId=Release-Notes-AFS-v22:AFS-features-updates-AFS-v22-r.html
Q.AFSのデーターをNutanix外にバックアップを取ることはできますか?
AFSは、NutanixのDataProtection機能を利用して、Nutanixクラスターをまたいでバックアップ及びDRの構成を作成することができます。この機能を利用することで、サービスを起動しているNutanixクラスター外にデーターを保存することができます。では、バックアップソフトウェア等を使ってバックアップを取得できるかというと、現状はバックアップソフトウェアによるバックアップは対応していません。
これは、AFSが、上記の通りABSを利用しているため、仮想マシンと紐づきがないボリュームのディスクが存在するためです。(詳細は、AFS(Acropolis File Service 2017/9/20公開予定)の紹介と導入方法 その4を参照)
今後NDMPへの対応等も検討されているという話を聞いていますので、今後に期待ですが、現状ではNutanixクラスター間のレプリケーションにお任せするのが最適解となります。
今回はAFSでよく尋ねられる5つの疑問について回答いたしました。
AFSは、まだまだ進化過程のアプライアンスですが、すでに実用的に利用できるアプライアンスです。Nutanixの無限のスケールアウトの便利さをファイルサーバーにも生かした機能であり、ファイルサーバーとして必要な機能はほとんど実装されていることから、簡易的かつファイルサーバーのサイジングが難しい場合に持ってこないソリューションだと思います。