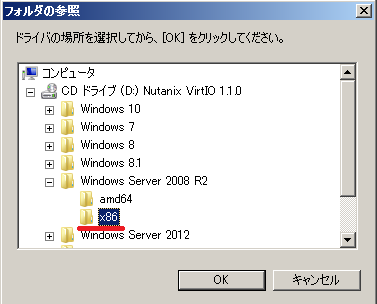Nutanixにおける、仮想マシン記憶領域を「ストレージコンテナ」といいます。
ストレージコンテナは、vSphereにあたるデーターストアーに相当します。
ただし、NutanixはシンプロビジョニングなストレージであることとNFS(NFS3)を利用してvSphereからアクセスされます。ちなみに、AHVからはiSCSIで、HyperVの場合は、CIFS経由してストレージアクセスを行います。
(ハイパーバイザーごとにストレージにアクセスされるプロトコルが異なります)
さて、Nutanixには、RAIDの概念やLUNの概念がありません。
また、ボリュームごとのストレージコントローラーのメインサブなどのボリュームとストレージコントローラーの紐付けなどの設定もありません。
今回は、このストレージコンテナの設定を確認していきましょう。
ストレージコンテナは、PRISM画面から作成します。
Storage Containerをクリックし、ストレージコンテナを作成します。
作成方法は簡単です。
コンテナ名を入れ、ESXiの場合マウントするESXiホストを入力すればそれだけで終わりです。
vCenter Serverから見るとストレージがしっかりとマウントされていることがわかります。
しかし、シンプロビジョニングのストレージであることから、いくつストレージコンテナを作成してもすべてが同じ容量で見えてしまいます。
従来のSANストレージの場合、用途に応じてRAID5や10などのRAIDレベルの変更や、ボリューム上に容量を設定し、リミットを決めたり等のことをやっていたかと思います。こういった運用は、Nutanixになっても可能です。
コンテナ作成時に出てる画面で「Advanced Setting」をクリックするとオプション画面が表示されます。
(参考)設定画面の全容
ここでは様々な設定を行うことができます。実際の設定を1つずつ見ていきましょう。
REPLICATION FACTOR
データーの冗長度を設定します。デフォルトのRF2は、元データーとそのデーターのコピーを1つ持つ形となります。RF3は、元データーとそのコピーを2つ作成する方法です。
容量は、Nutanixが保有する全体のディスクストレージ容量の約半分に相当するのがRF2、約3分の1に容量に相当するのがRF3になります。
RF3は、Nutanixのノードが5ノード以上必要となります。
RESERVED CAPACITY
ニュータニックスは、シンプロビジョニングなストレージのためコンテナを複数作ってもみな同じ容量で見えます。ただ、使える容量は実際のストレージ容量とREPLICATION FACTORの設定で決まりますので、実容量以上の容量は絶対に使えません。
そのため、あらかじめこの容量だけは確保しておきたいといった場合、このRESERVERD CAPACITYで、あらかじめ設定したストレージコンテナに設定したサイズの容量を占有確保させることができます。RESERVED CAPACITYで設定した容量は、他のコンテナからはマイナスされた容量で空き容量が表示されます。
例)例えば、ストレージコンテナが3つあり、空き容量が5TBだとします。この環境下でもう一つストレージコンテナを作成し、その際にRESERVED CAPACITYに1TBを設定すると、この他のストレージコンテナの空き容量は、4TBの表示に変更されます。つまり新しく作成したコンテナに1TBが占有で確保されたことがわかります。
(参考)Advanced Settingを何も入れなかった場合
(参考)Advanced Settingで、RESERVED CAPACITY設定を入れた場合
ADVERTISED CAPACITY
こちらは、ハイパーバイザーに見せる容量の上限値になります。
上記の例で1TBをRESERVED CAPACITYで占有予約容量とし、1TBをADVERTISED CAPACITYにした場合、このコンテナの容量上限値は1TBとして見えます
。
(参考)Advanced Settingで、ADVERTISED CAPACITY設定を入れた場合
COMPRESSION
ストレージの圧縮設定を行います。
圧縮は、ポストプロセスによる定期的な圧縮を行うための時間設定(Delay)を行うことができます。パラメーターに0を入れると、インラインの圧縮になります。
DEDUPLICATION
重複排除を行います。まずCACHEにチェックを入れ、キャッシュ層の重複排除を行います。CAPACITYのチェックを入れると、実容量の保存するストレージ領域に対して、重複排除が行われます。CAPACITYチェックボックスはCACHEのチェックボックスをクリックしないと有効になりません。これは、キャッシュ層でデーターのフィンガープリントの作成を行うためです。
DEDUPLICATION昨日で、CAPACITYの重複排除機能を利用するためにには、NutanixのPROライセンスが必要となります。
ERASURE CODING
冗長化したデーターの一部をパリティにし、実際のストレージ容量に対して、保存できる容量を増やす事が可能となります。
イレージャーコーディング機能は、NutanixのPROライセンスが必要となります。
(参考)重複排除とイレイジャーコーディングの設定画面
※PROライセンスガ適用されていないので、警告画面が表示されています。
FILESYSTEM WHITELIST
Nutanixで作成したストレージコンテナはNFSですので、Nutanix以外のハイパーバイザーからもマウントすることが可能です。その際、マウントするハイパーバイザーホストのIPアドレスをこのホワイトリストにあらかじめ登録しておく必要があります。
Nutanixは、従来のSANストレージに比べて大幅に楽に設定ができる割に、細かな設定ができることがわかります。IaaSなどのクラウドサービスを提供し、顧客ごとにLUNを指定容量に切ってQuotaの代わりに利用為ていた場合においても、Nutanixであれば、契約するユーザーごとにADVATISE CAPACITY設定を入れるだけで完了です。
従来のSANストレージでは、
- RAIDグループを作成
- ボリュームグループを作成
- LUNを作成
- メインコントローラーのパスを設定
- WWNゾーニング、ホストアフィにニティを設定
- ハイパーバイザーからマウント
といった手順をNutanixは、1つの画面で1分程度で作業を行うことができてしまいます。
Nutanixのすごさは、ハイパーバイザーとストレージが一緒に提供されますが、このような設定におけるメリットと同時に、従来までの運用や考え方を変えずにそのまま利用できる点は、Nutanixならではの点だと思います。